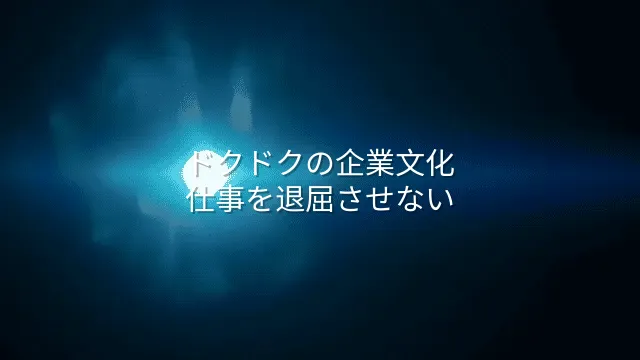
ディンタンでは、出勤は出社時刻を記録するためではなく、「モンスターを倒してレベルアップする」ためのもの。ここでいう「幸せ」はスローガンではなく、細部に隠された仕掛けのような存在です。たとえば毎週金曜日は「PPT禁止の日」。会議室はボードゲームルームに変身し、上司もインターンも一緒に「人狼ゲーム」で対戦。負けた人はチキンレッグのコスプレで『小さなリンゴ』を踊らなければなりません——間違いなく、CTOも実際に踊ったことがあります。 幸せとは放縦ではなく、仕事に「呼吸する余地」を与えること。ディンタンでは「フロー休暇」を導入。創造力が枯渇したと感じたら、1日「ぼんやり休暇」を申請できます。山登りでも、美術館鑑賞でも、あるいはただ寝るのもOK。会社はむしろSNSに投稿して#ディンタンぼんやり基金#をつけることを推奨しています。ある社員はこの休暇中にアイデアを思いつき、今では中国中の上班族が使っている自動承認機能を生み出しました。 さらにすごいのが「アンチ過労デー」。毎年1日、全社員の残業が禁止されます。総務チームがマイクを手にオフィスを巡回し、「まだ帰らないの?『最優秀過労王賞』を取りたいの?」と声をかけ、ポテトチップス一袋と「強制外出チケット」を手渡します。 ここでは、幸せこそが生産性です。社員が出勤を刑務と感じなくなるとき、アイデアは真夜中のひらめきのように、突然ひらめくのです。そして次のイノベーションの火花は、今まさに綿菓子を食べながらミーティングをしている午後に、どこかに潜んでいるかもしれません。
革新の連続:ディンタンのクリエイティブ文化
ディンタンでは、創造性はひらめきの偶然ではなく、毎日の習慣。まるで毎朝の出勤チェックと同じくらい自然なこと。ここでの合言葉は「アイデアが変でもOK。言わないことだけが問題」。社内には「アイデアマラソン」というイベントがあり、四半期ごとに開催。社員がチームを組んで自由奔放なアイデアを提出し、審査員を説得できれば実際に予算がつき、実行されます。あるエンジニアが「ディンタンカレンダーに集中用トマトタイマー機能を追加」と提案。それが実装され、今では最も人気のある生産性ツールの一つとなりました。 もっと面白いのが「逆方向ブレインストーミング」。上司が課題を提示すると、社員はわざと反対意見を述べ、どれだけ突っ込みを入れられるかで評価され、報酬も高くなります。「突っ込み文化」のおかげで、どの提案も徹底的に検証され、より堅実なイノベーションが生まれるのです。また「クリエイティブ酸素ルーム」というスペースもあり、ホワイトボード、レゴ、さらにはサンドバッグまで備え付け。社員はパンチをしながらアイデアを練り、ストレス解消とひらめきを同時に実現しています。 ディンタンは、「失敗してもいい自由」があってこそ、真の革新が生まれると信じています。あるプロダクトマネージャーが「音声スタンプ」機能を提案した際、「うるさいおばけパック」と笑われましたが、数か月後には若年層ユーザーの間で大ブレイク。会社が「試行錯誤」を後押しするからこそ、一見馬鹿げたアイデアもやがて大きな木に育つのです。ここでは、創造性は少数の特権ではなく、全員の日常的な呼吸のようなもの。
チームワーク:ディンタンの協働精神
ディンタンでは、チームワークはスローガンではなく、毎日上演される「連続ドラマ」です。この協働精神は、ちょうどよく調えられた炭酸飲料のよう。刺激があるのに、息苦しくない。毎週金曜の午後、エンジニアとデザイナーがオフィスの片隅で「レゴ城」を組み立てているのを見かけるかもしれません。これは幼稚な遊びではなく、部門を超えたクリエイティブ対決。あるいはマーケティングと技術チームが「脱出ゲーム」に挑戦し、論理とコミュニケーションで謎を解く——ついでに部署間の壁も崩しているのです。 ディンタンは「一緒に笑った仲間と、こそ本気で戦える」という真実を知っています。定期的なチームビルディング活動も、従来の形式とは一線を画しています。「逆面接の日」では部下が上司を評価。ランダムにマッチングして異なる部署の同僚と食事をする「ランダムランチ」では、食事中の会話から無数のコラボアイデアが生まれます。さらに「戦役プロジェクト」と呼ばれる跨部門プロジェクトもあり、「ディンシャン会議」の最適化プロジェクトでは、プロダクト、運用、カスタマーサポートが全員一丸となり、まるで臨時の特殊部隊のように、目標明確、役割分担は的確、コミュニケーションはゼロ遅延で動きます。 これらの活動は単なる娯楽ではなく、「私たち」という意識を、少しずつ社員一人ひとりの日常に「打ち込んで」いくものです。協働が習慣になると、効率は自然と高まります。だって、ディンタンでは、かつて一緒に脱出ゲームをクリアした仲間を、誰も裏切りたくないはずです。
学びと成長:ディンタンの個人成長プログラム
ディンタンでは、成長はスローガンではなく、日々踏みしめられる階段です。「出勤=出社、会議、PPT修正」と思っていませんか? 違います! ここでは社員たちがノートパソコンを抱えて「ディンタング学園」で最新のAI講座を争奪したり、「ハッカソンナイト」に参加してプロダクトの達人と直接対決したりしています。会社は学習をただ推奨するだけでなく、それをまるで大型リアルRPGゲームのように仕立て上げています。トレーニングを完了するたびに新しいスキルバッジがアンロックされ、年末には誰の「成長値」が高いかを競うのです。まるでゲームより刺激的です。 さらにすごいのが、キャリアパスがまるで「自分だけの冒険」を選ぶ小説のようになっている点。技術のスペシャリストになりたい? 専属のメンター制度があります。マネジメントに挑戦したい? まずは「小ディン訓練キャンプ」でチームリーダーの苦楽を体験。かつてコードしか書けなかったエンジニアの小李さんも、3年間の社内ローテーションでプロダクトやユーザーに触れ、今では跨部門チームを率いてヒット機能を開発。本人も笑いながら「母もやっと、私が会社でパソコンの修理をしてるんじゃないって気づいてくれたよ」と話しています。 ディンタンは、社員が成長すれば会社も大きく伸びると信じています。だから、進むべき道に迷っても心配いりません。ここでは、迷いさえも、思いがけない景色へと導くナビゲーションになるのです。
社会的責任:ディンタンの社会貢献活動
誰もが「出勤は刑務所入り」と嘆く中、ディンタンは静かに「社会貢献」を企業文化の中心に「打ち込んで」います。壁に貼られたスローガンではなく、時間とリソース、そして創造力を実際に投入して実践しているのです。テック企業の社会貢献といえば寄付? それは甘い考え。ディンタンのやり方は一味違います。
「公益ディン」機能をリリースし、企業ユーザーがワンクリックでボランティア活動に参加したり、歩数を寄付して植林に変えたり、ディンタンのコラボツールを使って地方の学校に遠隔授業を提供したりしています。社員には年1回の「有給社会貢献休暇」があり、家でだらけるのではなく、山奥で子どもたちにプログラミングを教えたり、動物保護施設で保護犬の里親探しを手伝ったりすることを推奨しています。あるエンジニアはこう笑います。「コードを書くのはプロセスの最適化のため。でも田舎で子どもたちがタブレットで授業を受ける手伝いをするのは、本当に人生を最適化しているって感じます。」
さらに徹底しているのが、サステナビリティを「システム化」している点。オフィスでは使い捨て食器を全面禁止。会議室の照明は室内人数に応じて自動調光。サーバーまでも省エネモードに最適化されています。これらは単なるPRではなく、プロダクト設計から日常運営まで、責任を一つひとつ「打ち込んで」いる証です。
ここでは、善行は自己満足ではなく、効率と創造性で善意を循環させる。世界を変えるのに、退職を待つ必要なんてない。今、この瞬間、「ディン」と押せばいいのです。
ドムテック(DomTech)は、ディンタンの香港における公式指定サービスプロバイダーとして、幅広いお客様にディンタンサービスを提供しています。ディンタンプラットフォームの活用についてさらに詳しく知りたい場合は、オンラインカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。また、お電話(852)4443-3144またはメール

 日本語
日本語
 English
English  اللغة العربية
اللغة العربية  Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia  Bahasa Melayu
Bahasa Melayu  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Tiếng Việt
Tiếng Việt  简体中文
简体中文