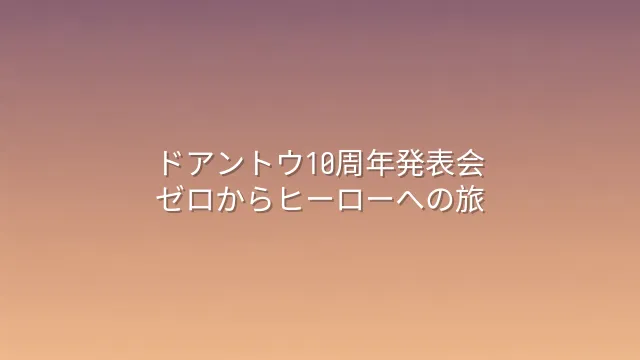
「ピン——」この通知音が、10年前には誰も想像しなかった数億人のビジネスパーソンの「目覚まし時計」となるとは。当時のスマホの通知欄は、まる春節前のスーパーのようにさまざまなSNSアプリで埋め尽くされていたが、唯一「仕事モード」に特化した避難所だけが欠けていた。ディンディン(DingTalk)は、阿里巴巴(アリババ)内部のエアコンさえ修理しない会議室でこっそりと生まれた。その動機は単純すぎて笑ってしまうほどだった。「上司が部下に連絡できるように、社員が『既読無視』できないようにする」ことだ。
当時、通信業界の大手が虎視眈眈と狙いを定め、数え切れない企業向けコラボレーションツールが「革命児」を名乗っていたが、大半は「一度使ってアンインストール」される運命に終わった。しかしディンディンは逆を行った。派手なフィルターもなければ、限定ストーリー機能もない。「見た目は悪いけど使いやすい」を主軸に、「既読機能」を殺し文句の特徴とした――人を苦しめるためではなく、コミュニケーションに痕跡を残すためだ。誰が想像できたろうか、「忙しいふりができない」アプリが、経営者たちの心の中の白月光(理想の存在)になるなんて。
初期の開発チームは自分たちのことを「オフィスのゴキブリ」と呼んでいた。コミュニケーションの穴があるところへどこへでも這い寄っていったのだ。小さなチームの勤怠管理から大企業の承認プロセスまで、ディンディンは一つ一つ課題を噛み砕いていった。まるでかつてアリババが靴下販売から始まったときの執念そのものだ。誰にでも好かれる必要はない。ただ「使ったら離れられなくなる」ことだけを目指した。こうして、無数の「了解、返信ください」の夜を重ねながら、ディンディンは静かに根を下ろしていった。
成長の道:ユーザーと機能の拡大
もしディンディンの誕生が「追い込まれた末の起業物語」だとすれば、その後の10年間はまさに企業コミュニケーション界の「レベルアップ&ボス戦」の大冒険だった。当初はアリババ内部の「家族のみ使用」から始まり、今では数億人のユーザーを抱えるまでに至ったディンディンの成長軌跡は、まるで熱血アニメのようだ――主人公が初心者からスタートし、スキルを習得し、仲間を集め、ボスを倒し、最終的には会社全体を救うヒーローとなるストーリーだ。
初期のディンディンは、控えめな技術オタクのような存在だった。機能は多くないが、極めて実用的だった。「既読/未読」機能はすぐに上司たちの心をつかみ、「DING一下(ピンッと通知)」機能で遅刻しがちな社員も即座にハッとするようになった。一見シンプルなこれらの機能は、実は企業内コミュニケーションで最もイライラするポイント――メッセージが届かない、タスクが進まない、会議が延々終わらない――を正確に突いていたのだ。
ユーザー層が大企業から中小企業、さらには学校やマンション管理組織にまで広がるにつれ、ディンディンも猛烈に進化を始めた。出勤打刻、承認申請、スケジュール管理、クラウドストレージ、ビデオ会議……機能は多すぎて、まるでオフィス版スイスアーミーナイフのようだ。さらにすごいのは、「段階別アプローチ」を理解している点だ。小規模企業はその簡単操作を愛し、大企業はきめ細かいプロセス管理に魅了される。先生たちは出席確認に使い、保護者グループも「了解の方は1と返信ください」のスパム投稿から解放された。
これは偶然ではない。「コミュニケーション不全症」に対する精密な治療法だ。各機能の裏には、徹夜続きのプロジェクトグループや納期に追われるデザイナー、精神崩壊寸前の事務スタッフたちの血と涙の歴史がある。ディンディンは単なるツールではなく、職場人たちの「救世主」だったのだ。
技術主導:ディンディンの革新と変革
「10年前、私たちが欲しかったのは、出勤打刻のために並ばなくて済むシステムだけでした。」ディンディン創業者の冗談めいた一言が、技術革新の幕開けを告げた。だが誰が予想できただろう、この小さな種が、何千万もの企業を支える巨大なテクノロジーの木に育つとは? 10周年発表会で、ディンディンはもはや「チャットツール」ではなく、AIという鎧を纏い、クラウドのロケットに乗った効率化の預言者となっていた。
イベントでのデモンストレーションでは、AIアシスタントが疲れ知らずの事務担当のように、会議の要点を自動要約し、方言の音声を翻訳し、上司がまだ口にしていない「あのレポート」を予測までしていた。その背景には、ディンディンが独自開発した大規模モデルとアリババクラウドの「飛天(フェイテイエン)」システムとの深いつながりがある。単に「AI」というラベルを貼るのではなく、メール、承認、通話の一つひとつに知能を織り交ぜているのだ。
さらに強力なのが「クラウドネイティブアーキテクチャ」の全面的アップグレードだ。企業はサーバーのクラッシュで夜を明かす必要がなくなり、ディンディンのスケーラビリティは呼吸のように自然だ。ある製造業の顧客はこう語る。「以前はシステムが止まると工場全体が停止したが、今は生産ラインのデータがリアルタイムで同期され、トイレのドアの修理依頼さえ自動で作業員に割り振られる。」
技術はもはや冷たいコードではなく、コミュニケーションのすき間に潜む潤滑油となった。他社がまだ「デジタルトランスフォーメーション」を語っている間に、ディンディンはAIとクラウドコンピューティングを使って、オフィスを思考する有機体へと静かに変えつつある。
エコシステム:ディンディンのパートナーとエコ構築
ディンディンの技術革新がスーパーヒーローの内功(ナイトメアトレーニング)だとすれば、そのエコシステムは壮大で賑やかな「アベンジャーズ」のような存在だ――各パートナーが独自のスキルを持ち、共に敵と戦い、レベルアップしていく。10周年発表会では、ディンディンは単に性能を見せつけるだけでなく、「友達紹介」も披露した。SAPからユーヨウ(用友)、小冰公司からファンウェイ(泛微)まで、数百社のパートナーが一列に並ぶ様子は、まるでテック業界のレッドカーペットイベントのようだった。
しかし、これは普通の提携関係ではない。「共生関係」という深い結びつきだ。ディンディンはオープンプラットフォームとAPIを提供し、開発者がレゴブロックのようにCRM、ERP、HRシステムを自由に組み込めるようにしている。想像してみてほしい。あなたの出勤管理アプリが単に打刻するだけでなく、自動で経費精算を起動し、プロジェクト進捗を同期し、会議室のコーヒーまで予約してくれる――これこそがエコシステムの力だ。
もっと面白いのは、ディンディンがプラットフォームであると同時に、「インキュベーター」にもなっている点だ。低コード開発ツール「宜搭(イータ)」をリリースし、プログラミングがまったくわからない事務スタッフでもアプリを開発できるようにした。結果どうなったか? 企業内で数千ものオリジナルアプリが次々と生まれ、ディンディンは瞬く間にコミュニケーションツールから「企業デジタル化エンジン」へと変貌した。これはエコ構築というより、まるでテクノロジー版『創造101』だ。実力のある者が次々とデビューしていく。
他人がまだ機能競争をしている間に、ディンディンはエコシステムで競合を圧倒していた――一人で走るよりも、皆で歩けば遠くまで行けるからだ。
未来展望:ディンディンの次の10年
10年の歳月が、ディンディンのグループチャットで積み上がる未読の赤いドットのように山積みになったとき、この10周年発表会はまるでテクノロジー界の春節晚会(旧正月のテレビ番組)だった――花火、サプライズ、そして「それもできるの!?」と驚くような新機能の数々。壇上のスピーカーが冷静に言う。「我々はチャットツールではない。企業の神経中枢だ。」 聴衆は一瞬で気づいた。毎日「@」される苦しみは、実は職場のスーパーヒーローに進化するための通過儀礼だったのだ。
次の10年はどうなる? ディンディンは穏やかなオフィスの世話係には留まらない。これからは「スマート意思決定の演出家」になる。近日リリース予定のAIアシスタントは、会議の要点をまとめるだけでなく、上司の口調から「さっきの『もう少し検討しましょう』は本気の迷いなのか、それとも皮肉なのか」まで判断できるようになる。さらに驚くべきことに、新バージョンには感情分析機能が統合され、どの部署の社員が残業過多で集団的に仙人化(精神的限界)しそうかまで管理職に知らせる。
テンセントの「腾讯文档(テンセント文書)」や「飛書(フェイシュウ)」といった「隣のライバル」たちの猛追に対して、ディンディンの戦略はシンプルだ。あなたが機能で勝負するなら、私はテーブルごとひっくり返す――エコシステムを宇宙へと拡張する。ハードウェアメーカーと協力し、「スマートIDカード」を発売。社員がオフィスに入ると自動で打刻、照明点灯、個人専用の出勤BGM再生まで可能に。コーヒーを淹れるまでしかない。

 日本語
日本語
 English
English  اللغة العربية
اللغة العربية  Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia  Bahasa Melayu
Bahasa Melayu  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Tiếng Việt
Tiếng Việt  简体中文
简体中文